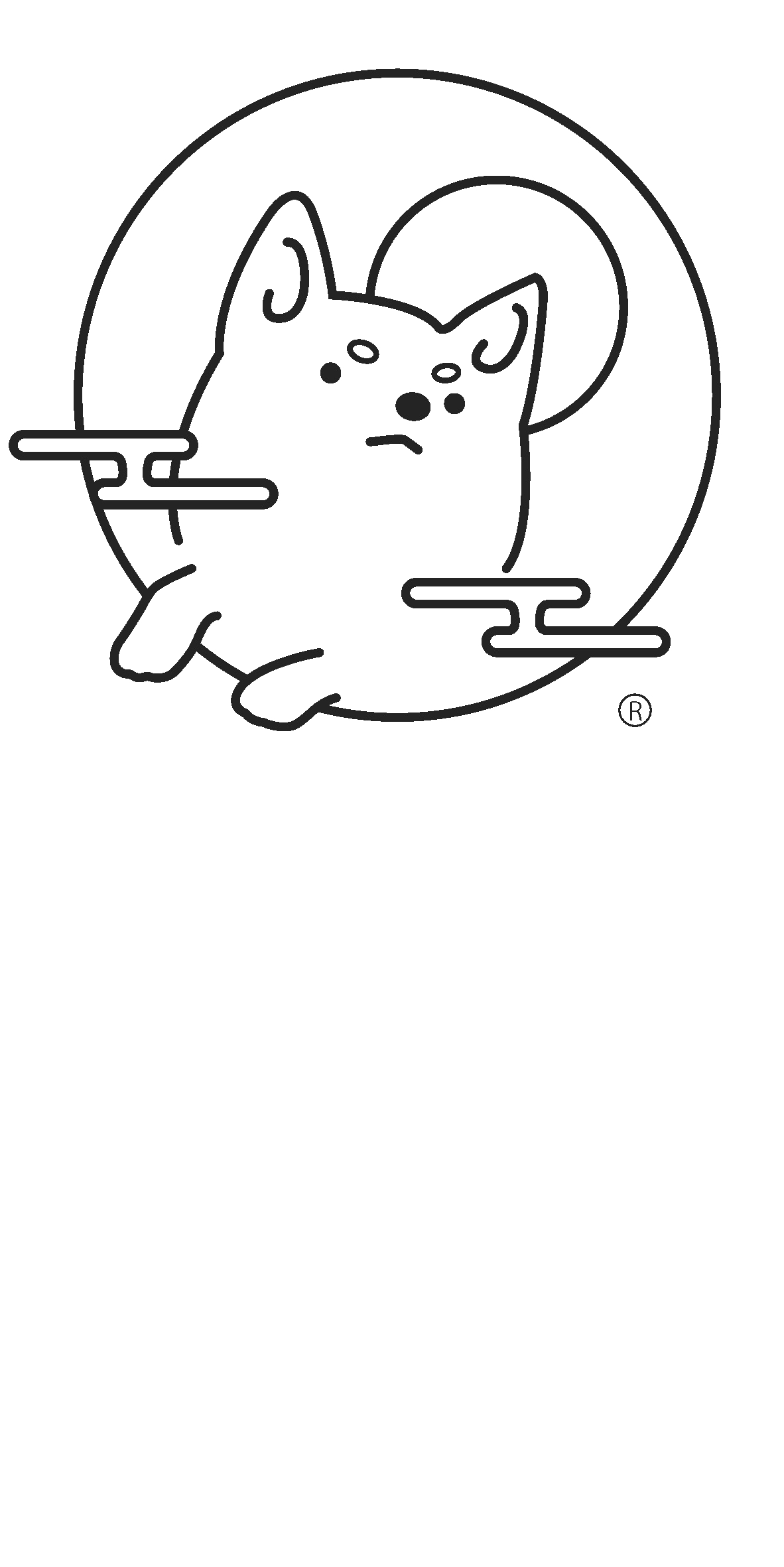琵琶湖周辺の里山のやさしい暮らしを未来へ
私たちNPO法人おおたき里づくりネットワークは、滋賀県多賀町大滝地域で活動するまちづくりNPOです。多賀町は「多賀大社」で有名な観光地ですが、大滝地域は一山越えた中山間地域。人口減少、少子高齢化が顕著な地域です。
地域の持続可能性を如何にして創造するか。2020年8月から地域住民と学識経験者、行政で1年8ヶ月かけて議論してきた地域づくりの思いを実現する組織として、2022年4月に生まれたのがNPO法人おおたき里づくりネットワークです。
大滝地域は琵琶湖に流れる一級河川犬上川の流域14集落で構成される地域。鈴鹿山系の清流に育まれた、豊かな自然環境を有する地域です。
きれいな水で栽培されるお米や野菜はとてもおいしく、川で捕れるアユやイワナも好評です。地元の大滝小学校や、たきのみやこども園の子どもたちは、自然環境の中で元気に育っています。
ぜひ大滝小学校のPVをご覧ください!この里の環境に育まれたステキなやさしい暮らしがあります。
私たちのミッション

この里山で育まれてきた「やさしい暮らし」を未来に継承することが、私たちのミッションです。
そのためにも特に、地域に雇用を創造することが必須です。
NPOの活動は、現時点では多賀町の協力で地域おこし協力隊で行っています。協力隊の任期は3年。協力隊が卒業しても地域で「やさしい暮らし」を実践できるような雇用環境を生み出したいと考えています。
酒蔵再生で活動拠点を確保し、里山の「やさしさ」を届けるお酒を開発

里山の地域資源を活用した「やさしい暮らし」の再興。
そのスタートとして、地域に残る廃業した酒蔵をリノベーションし、地域資源を活用し時代に合わせた「新たな酒造りの拠点」を創造し、里山の「やさしさ」を届けるお酒を開発します。
酒造りで注目した酒類は「粕取り焼酎」

日本酒の製造課程で出る「酒粕」をアップサイクルした焼酎です。日本酒らしさもありつつ、日本酒とはまた違った風味を持つお酒です。
かつてはどの日本酒蔵でも製造していましたが、近年製造する酒蔵は激減し、滋賀県内では、草津市の「太田酒造」さんのみ。酒粕の多くは廃棄物として処分されています。
酒造りは、まずは地域資源を活かしたリキュールづくりからスタートし、最終的には、蒸留器を導入し、酒粕のアップサイクルを目指します。
滋賀県内の酒蔵と連携し酒粕のアップサイクルを行い、その原酒と地域資源をブレンドした「やさしいお酒」をつくっていきたいと考えています。
里山から生まれたこのお酒が、皆さんの暮らしに「やさしさ」を届けることができると信じています。
プロジェクトリーダー

岩下晃士(いわした こうじ)です。1989年、熊本県熊本市生まれ。縁あって、多賀町地域おこし協力隊として2022年11月から活動を行っています。使われなくなった酒蔵や地域の農産物など、地域資源を活用した地域活性化を実践したいと思い、プロジェクトを立ち上げました。飲食店やベーカリーでの経験、滋賀県立大学での地域活性化の学びを活かし、みなさまに里山のやさしいお酒をお届けできるよう頑張ります
里山浸酒(SATONOWA SHINSHU)

県内で唯一、粕取り焼酎を製造している太田酒造さんにご協力いただき、太田酒造さんの粕取り焼酎(大吟醸)を原酒として、地元多賀で農薬不使用で農業に取り組む「もんてくーる」さんに栽培いただいた「ビーツ」を中心に様々なハーブをブレンドしたリキュールをOEM製造しました。
ラベルデザイン

里和浸酒:ビーツ No.01 のラベルは、滋賀県彦根市在住のアーティストの上田三佳さんにプロジェクトへの協力をお願いしました。現地にお越しいただいて、お話しさせていただいて、ステキなラベルが生まれました。
酒蔵、再生。クラファン実施中!

プロジェクトでは現在、酒蔵のリノベーションを推進中です。拠点整備を目的としたクラファンでは、おかげさまで目標金額を達成することできました。引き続きリノベーションWSを開催しています。是非応援ください!
シリーズ展開、そして世界へ

プロジェクトは、酒粕をアップサイクルする事業として、第壱話から第参話の3ステップで物語を紡ぎます。
現段階は、OEMでの製品の開発段階ですが、プロジェクトの展望としては、まずは、自分たちで酒粕の蒸留を実践できるようになり、滋賀県内の31蔵の日本酒蔵の酒粕をアップサイクルしたリキュールを製造できるようになればと考えています。そして、近い未来、里和浸酒が世界に拡がっていくことを夢見ています!